離職票が届かない場合の失業給付の仮手続き
離職票が届かない場合の失業給付の仮決定手続き
Q 正社員として働いた会社を退職しました。失業給付を受給したいので会社へ離職票の作成を依頼しましたが、退職して20日以上経っても未だに離職票が送られてきません。どうしたらよいでしょうか。
----------------------------------------------------------------------------------------------
A 失業給付の申し込みには原則、離職票が必要です。会社に離職票の発行を依頼すると、退職後2週間前後で手元に届くのが一般的です。しかし、事業所による手続きの遅延や郵送の遅延などにより手元になかなか離職票が届かない場合は、退職日の翌日から12日目以降であれば、ハローワークで「受給資格の仮決定手続き」ができます。
この手続きをすると、後日離職票が届いた際に、仮決定手続きをした日までさかのぼって受給資格があったとみなされるため、離職票が届いてから手続きするよりも早く失業給付を受給できます。
まずは「離職票が届かず失業給付の受給手続きができない」と、住所を管轄するハローワークへ相談しましょう。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
事業主は、労働者が退職等により雇用保険の被保険者ではなくなった場合、その事実があった日の翌日(離職日の翌々日)から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出しなければなりません。また、失業給付の受給に必要な離職票は、労働者から発行希望がある場合や、退職時点の年齢が59歳以上の労働者には必ず作成しなければなりません。(退職後でも離職票の作成依頼は可能)
離職票が届かない場合の仮決定手続きは、「とりあえず失業給付を受給する意思を伝えるため」のものです。退職日の翌日から12日目以降であれば、ハローワークで手続きが可能です。離職票の提出で本決定となり、手続きした日までさかのぼって失業給付の受給資格が決定されます。給付制限がない場合は、最初の認定日から1週間程度で失業給付が支給(指定口座へ入金)されます。
例)令和8年2月5日付退職の場合→令和8年2月17日から仮手続き可能
| 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 |
| 退職日 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 仮手続き可能 |
・離職票提出後の「受給資格の決定」がスムーズに進む。
・予め仮決定手続きをすることで、離職票が届いてからの手続きに比べ失業給付の受給までの期間が短縮できるため、安心して求職活動に専念できる。
・失業給付の受給手続きが遅れると、所定給付日数のすべてを受給できなくなることがあるが、仮決定手続きをすることで受給期間(原則離職の日の翌日から1年間)の確保ができる。
(受給期間を過ぎると給付日数が残っていても失業給付は支給されません。)
★ハローワークで仮決定手続きを希望する際には、以下の2つを窓口で伝えましょう。
・既に会社へ離職票の発行を依頼しているがまだ手元に届いていないこと。
・ハローワークへの相談が退職日の翌日から12日目以降であること。
<仮決定手続きに必要なもの>
・身元確認書類(必ず持参:マイナンバーカード等)
・写真2枚(後日でもよい:マイナンバーカードの毎回提示により省略可能)
・本人名義の通帳またはキャッシュカード(後日でもよい)
・退職した日がわかる書類(離職日を確認するため:準備できなくても手続き可能)
などが必要となるので、ハローワークで確認しましょう。
<受給資格の仮決定手続き後の流れ>
- 仮決定手続きの際、必要書類を受け取り、今後の流れの説明を受ける。
→仮決定手続きをした日から「通算7日間の待期(給付対象外)」がスタートする。
- 説明された雇用保険説明会へ出席し、求職活動をした上で、指定された認定日に出席する。
→仮決定手続きであっても、通常の失業給付と同様に求職活動の実績が必要です。
★仮決定手続き後に離職票が手元に届いたら、速やかにハローワークへ提出しましょう!
仮決定手続きから4週間後(28日後)の認定日までに離職票を提出すること。
→認定日までに離職票の提出がされない場合は、認定が保留され、失業給付の受給開始が遅れる場合があります。
★なかなか離職票が届かない場合で認定日が迫っているときは、前職の会社に再度問い合わせると ともに、その旨をハローワークに相談しましょう。
注意☝
退職日について会社と労働者との意見が異なる時は、改めて受給手続きが必要となる場合があるので、詳しくはハローワークに相談しましょう。


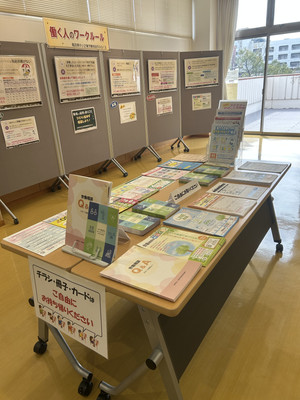

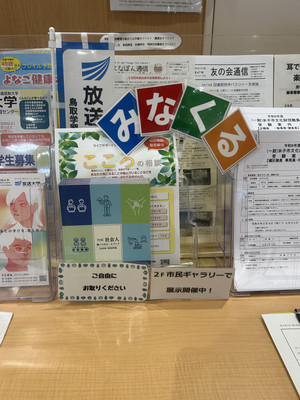


 学生たちは、ワークを真剣に取り組んでいて、進んで発表もしてくれました。
学生たちは、ワークを真剣に取り組んでいて、進んで発表もしてくれました。 このような感想がいただけとても嬉しく感じ、また、社会に出て困った時に少しでも
このような感想がいただけとても嬉しく感じ、また、社会に出て困った時に少しでも
